年商1兆円超え!ゼネコン「清水建設」のお仕事のヒミツ『がっちりマンデー!!』
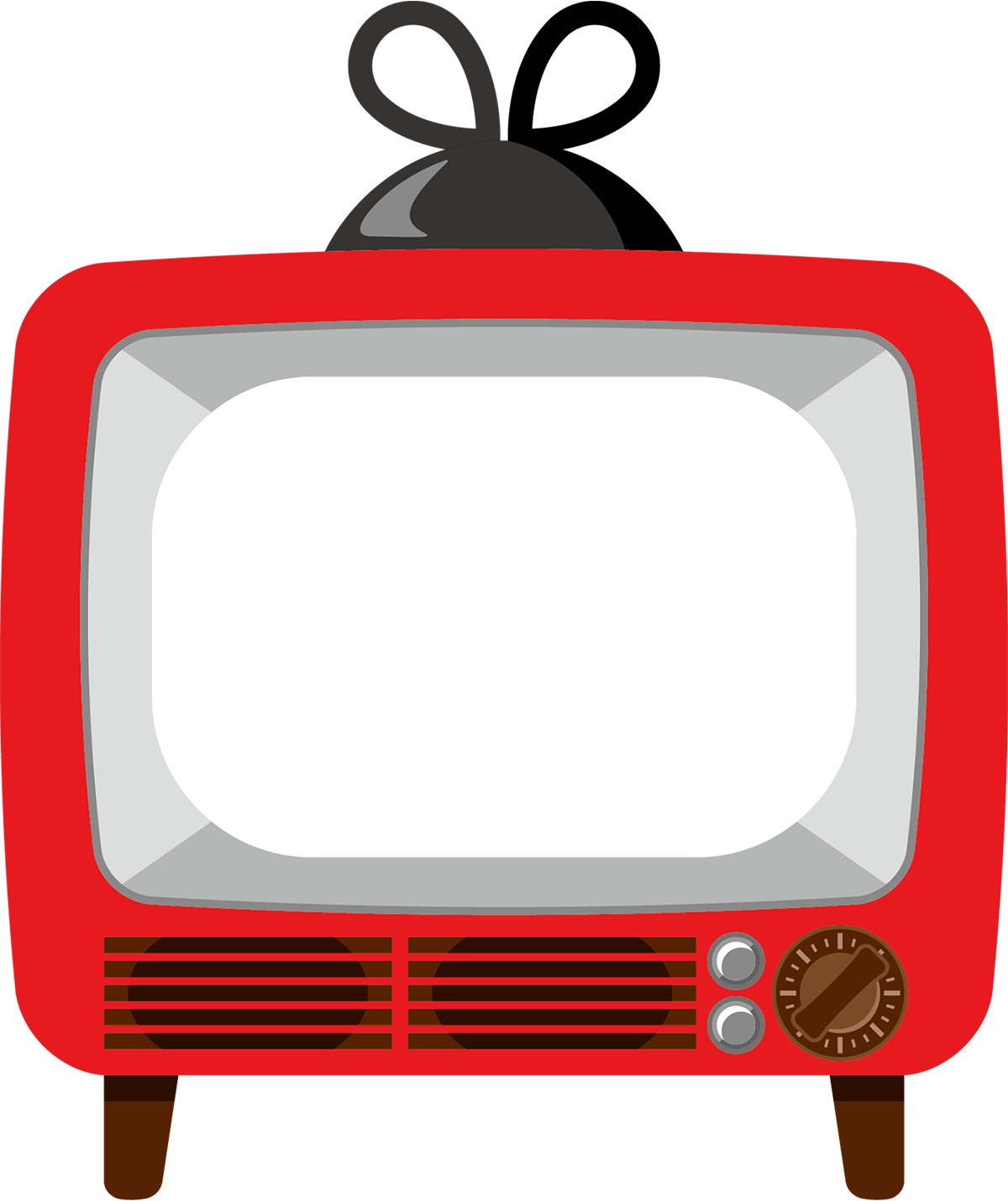
2010/8/25放送の『がっちりマンデー!!』。
今回は「ゼネコン・清水建設」がテーマです。
ゲストは清水建設株式会社代表取締役社長の井上和幸さんです。
「ゼネコン」とは General Contractor の略であり、大きなビルや商業施設を作ったり、高速道路やダムなど重要なインフラを作ったりして日本の街づくりを支えるスーパー建設会社のことです。
そんなゼネコンの中で、今回は清水建設が登場します!
この会社は全国でもちょっと独特で、創業は1804年(江戸時代)に宮大工の清水喜助が作った小さな会社が始まりです。
いまや従業員数が1万6000人以上、売り上げは年間1兆7000億円。
ビルに道路に神社仏閣まで、全国で建物をづくりまくっている日本屈指の建設会社なのです!
そこで今回は清水建設、知られざるゼネコンのお仕事をご紹介します。
ゼネコンのお仕事:道路づくり
清水建設の大事なお仕事の一つが「道路づくり」。
まずスタッフが向かったのは、新東名高速道路の川西工事の現場です。
現在こちらでは新東名高速道路の伊勢原JCTから御殿場JCTまでの48キロの道路を建設中です。
工事費はいくらかかるの?
この工事で清水建設が担当している分が約230億円の費用なっています。
まさに日本の大動脈となる高速道づくりです。
しかし、トンネルらしきものが見えるけど、道路はどこにもありません。
地面が低くなっているところにどんどん土を盛り上げて道路を作っていくのです。
高さ70mにまで土を積み上げて道路の土台を作っています。
使われる土の量はなんと10tトラック70万台分です。
道路づくりのココが大事:土の管理
実は大規模な道路づくりでとても大事なのが土の管理です。
高速道路というのは安全に走行するために、できるだけまっすぐ作るようにしています。
そうするとこういう山間部での工事ではかなりの土が発生します。
山の中にまっすぐな道を通すには、ある場所は土を削り、ある場所は土を埋める。
もし土が余ったら処分するのにかなりの額のお金がかかるので勝手に処分するわけにはいきません。
土を余らせず不足させないようにようにするのがもう道づくりの腕の見せ所ですってね。
道路づくりのココが大事:土の硬さを作る
そして土を使った道路の土台作りでもう一つ大事なのが、土の硬さを作ることです。
ポイントは固め方です。
土の性質によって最適な締め固め回数があり、土の種類に合わせてローラーで土を踏む回数がちゃんと決まっています。
粘土系の土は踏む回数が4回、
砂利がある土は踏む回数が6回、
岩石がある土は踏む回数が8回。
踏む回数が少なすぎるとしっかり固まらないし、多すぎるとか却って柔らかくなってしまうとか。
場所や回数は「転圧管理システム」で管理
土を踏んだ場所と回数が色でわかる「転圧管理システム」がローラーの運転席に取り付けられており、常にチェックしながら運転しています。
清水建設が独自開発したこのシステムのおかげで間違いが減り、作業スピードも格段にアップしたのです。
道路づくりのココが大事:とにかく安全第一
続いてスタッフが向かったのは、トンネルの掘削現場。
トンネルづくりで大事なことは、とにかく安全第一です。
そこで、掘削作業の最前線へ。
そこには爆薬を仕掛ける穴を掘るマシーン「ドリルジャンボ」がありました。
今回は20ヶ所に火薬を装填します。
爆薬専門の作業員たちが、爆薬を穴にどんどん詰めていきます。
最後に導火線を1本にまとめたら点火スイッチを押す作業員が一人発破の点火場所に移動します。
するとトンネル内に音楽が流れました。
この音楽は「5分の間に避難しろ」という合図です。
合図を知らせる曲は現場担当が決めているとのことです。
点火者以外は急いで150メートル離れた場所へ退避します。
1回の発破で掘削できるのはおよそ1 mであり、これを1日最大5回行うこともあります。
派手に見えるけど地道な作業なのです。
皆さん、安全第一でがっちり!
ゼネコンのお仕事:ビルづくり
清水建設、メインの仕事といえばやっぱりビルづくりです。
GINZA KABUKIZAやコクーンタワーに山王パークタワーなど100m超えのビルをガンガン作っています。
では、ビルづくりには一体どんな難しさがあるのでしょうか?
そこで今回はめったに入ることのできない建設中の現場を特別に案内してもらえることになりました。
都心のど真ん中に、高さ150 mの高層ビルを建設中の現場です。
お店やオフィスなどが入る複合施設が2021年に完成予定です。
そんなビルづくりで最も大事な現場があるということで、地下へ。
ビルづくりのココが大事:建物を支える杭
地下2階の下が建物の土台の基礎になりますが、この基礎の下に建物の一番大事な杭があります。
今回は杭が68本で地上から40m下まであります。
ビルづくりで一番大事なのは建物よりもその建物を支える杭の方。
高さ数十mもある筒状の鉄筋を地下までに掘削した穴に下ろしてコンクリートを流し込んで固めたら完成です。
(杭は打ち込むじゃなくて流し込むんですね)
そして、杭づくりで重要なポイントが真っすぐ打つこと。
1本でも杭が傾いているとがっちり支えられないどころか、ビルが傾いてしまう虞もあります。
慎重にも慎重を期さないといけないのです。
今回は68本ありましたが、全部打ち込むのに3ヶ月半かかりました。
ビルづくりのココが大事:スケジュール管理
そしてもう一つ大事なことはスケジュール管理です。
この日は2階床部分をコンクリートで固めていく作業でした。
では、どんなスケジュール管理が必要なのでしょうか?
今日は1時間8台ペースでミキサー者が44台入ってきます。
コンクリートなどの搬入スケジュール表によるとミキサー車が11時から17時の間で1時間に8台、計44台が来ることになっています。
さらに建設現場まで1時間以内に搬入できる生コン工場を選んでいます。
時間を決めてやらないと、生コン自体の品質が悪く(固まって)しまいます。
夏の時期だと製造してから90分以内でコンクリートを流し込むようにしています。
つまり、搬入が遅れるとミキサー車の中のコンクリートが固まってしまい使い物にならなくなります。
そうなると作業時間もコストも余計にかかってしまうのです。
なので、ゼネコンである清水建設がしっかりスケジュール管理をしているのです。
都心の混雑する道の中でスケジュール通りに1時間に8台到着し、現場の作業予定通りキレイに仕上がるってわけです。
ビルづくりのココが大事:設計図通りつくる
続いてのビルづくりの現場は神奈川県横浜市にある横浜グランゲート、19階建てのビルです。
中ではエレベーターのレールの取り付けの真っ最中。
この作業で大事なのは設計図通りつくること。
実はビルづくりではわずかながらミリ単位でズレが生じることがあります。
そのため、エレベーターのレールを1階から最上階までまっすぐに取り付けるのはかなり難しいです。
しかもレールがまっすぐじゃないとエレベーターがグラグラ揺れたりしてとても危険です。
そこで作業員は、ピアノ線を基準にしてまっすぐかどうかチェックしています。
ピアノの線から距離がいくつかということでカゴの動くレールを合わせています。
清水建設はビルづくりでがっちり!
ゼネコンのお仕事:伝統建設の復原工事
そしてもう一つ清水建設の建物づくりの原点ともいえる大事なお仕事が伝統建設の復原工事です。
清水建設は創業者が宮大工出身ということもあり、昔から伝統建築物の改修・修繕や復原工事に携わってきました。
出雲大社や東大寺大仏殿など日本全国で国宝級の伝統建築物の改修・修繕作業をガンガン手がけているのです。
現在、奈良県・朱雀門の真向かいにある784年の奈良時代に建てられた平城宮大極殿院南門を復原中です。
中では宮大工さんたちがが完成に向けて作業の真っ只中。
伝統建築物を建てるのには独特の難しさがあるといいます。
伝統建設 ココが大事:木材の確保
そこでやってきたのは木材の保管庫。
やはり一番大事なのは木ですね。
木の調達をいかにするかということが一番大事です。
伝統建設 ココが大事:当時と同じ材料を使う
伝統建築の難しさはなるべく当時と同じ材料で再現しないといけないということです。
今回は入手が難しい高級木材ヒノキを使います。
これだけの立派なヒノキをどうやって集めたのでしょうか?
清水建設は大手ゼネコンの中で唯一、社寺建築部門を置いています。
そのネットワークを生かし、当時使っていたであろう吉野のヒノキを大量に調達したのです。
伝統建設 ココが大事:宮大工
そして当時を再現する上で欠かせないのは宮大工の皆さん。
年々減ってきている宮大工を日本中から集めるのも清水建設の大事な仕事なのです。
伝統建設 ココが大事:当時と同じ道具を使う
しかも宮大工が使うのはその当時と同じ道具だといいます。
例えば「槍がんな」と呼ばれる奈良時代に使われていたかんな。
削りだすと表面が波打ったようになるのが特徴です。
なぜ当時使われていたのが「槍がんな」とわかったのでしょうか?
大カンナができるまでは「槍がんな」で仕上げをしていたと絵巻物に記録が残っていたので、当時と同じように「槍がんな」をつかっているとのことです。
清水建設は平城宮大極殿院南門を3年後の2022年完成に向けて鋭意復原中です。
所感
建設現場っていつもシートに覆われていて中の様子が見えないんですよね。
あのシートの向こうでどんな職人がどんな凄いマシーンや道具を使ってあんな大きな建物を作っているのだろう?と幼心に憧れを抱いていました。
大人になった今でも工事現場の様子をみるとワクワクします。
今回は楽しい番組でした。

フォローお願いします