明らかになった肩こり、腰痛の原因!その予防と改善方法『健康カプセル!ゲンキの時間』
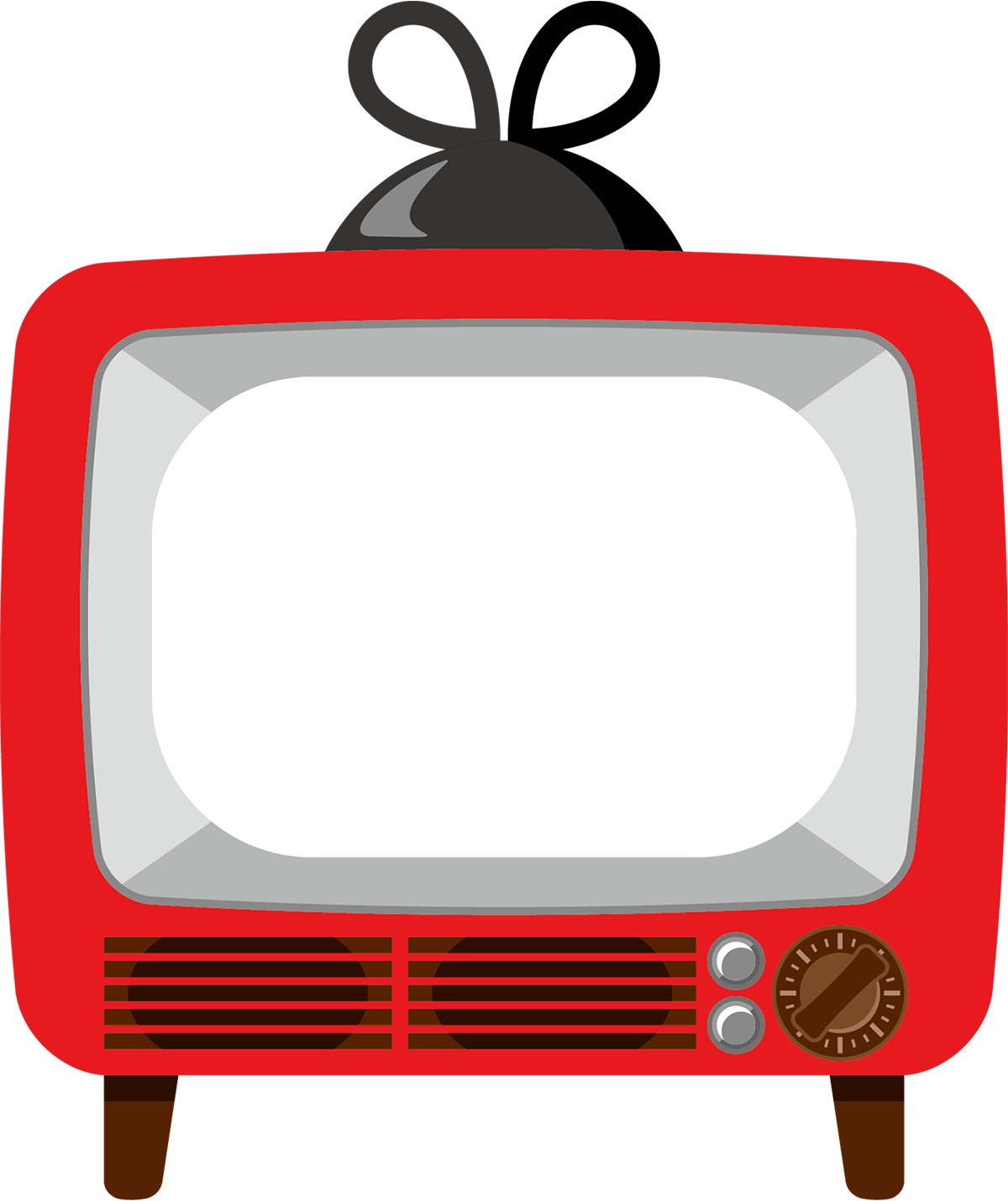
今日の『健康カプセル!ゲンキの時間』のテーマは「クロスシンドローム」です。
年を重ねるとともに関節痛、肩こりなど体のあちこちに不調を感じる方も多いのではないでしょうか?
しかし、近年その意外な原因が明らかになりました。
それは、「クロスシンドローム」です。
実は、腰痛などの不調の原因が一見全く関係なさそうな箇所にあるというんです。
そこでは体の不調の「クロスシンドローム」に迫ります。
北里大学大学院整形外科学教授医学博士高平尚伸先生が解説します。
不調の原因はどこにあるのか?
今回は体の不調になる方に集まっていただきました。
山崎さん(男性):腰痛歴3年
デスクワーク中心のサラリーマン
疲れがたまると腰が重くなる。
松谷さん(女性):腰痛・肩こり歴3年
主婦業をしながら週5で働いている。
肩と腰がすごく痛い。いつも誰か1人を背負って生活しているような感じ。
不調の原因を探るべく、やってきたのは、北里大学。
体の動きと健康の関係に詳しい高平先生に話を伺います。
靴下を使ってチェック
立ったまま靴下をはいてみてください。
まずは山崎さんから。
ふらついてなかなか履けません。
山崎さん、もう少しのところで断念。
続いて松谷さん。
ふらついて履けませんでした。
2人ともうまく靴下がはけませんでしたが、このチェックで何がわかるでしょうか。
腸腰筋の筋肉が衰えている?!
靴下をはいたときにかなり体が揺れていました。
これはバランスが崩れているんですね。
バランスが崩れているのは腸腰筋が衰えている可能性があります。
腸腰筋は普段はを見ることも触ることもできない筋肉なのでMRIで見てみることに。
まずは山崎さん。
まずは平均的な男性と山崎さんの腸腰筋の太さ比べてみるも一目瞭然。
山崎さんの筋肉がやせ細っているのが分かります。
続いて、松谷さん。
まず正常な50代女性と松谷さんを比べます。
やはり腸腰筋の太さが違いました。
2人とも腸腰筋が衰えていることが判明。
腸腰筋とは
名前から分かるように、大腸のある腰あたりと背骨の背骨の間、つまり、体の中心部に位置し上半身と下半身を繋ぐ大切な筋肉です。
主な働きは歩くことなど足を前後するときです。
腸腰筋がしっかりと働いてくれることで、私達は歩くことができるんです。
また、正しい姿勢で座ることができるのも、腸腰筋が働いているお陰です。
腸腰筋は下半身のバランスを保つ非常に重要な筋肉
さらにもう一つ重要な役割があります。
腸腰筋は身体の中心あたりに位置するので下半身のバランスを保つ非常に重要な筋肉です。
さっきの靴下でチェックしていたのは腸腰筋の衰えをみていました。
靴下を履こうと太腿上げたとき、腸腰筋が正常であれば、しっかりと上半身のバランスを取ることができます。
しかし、腸腰筋衰えると上半身をうまく支えられず、バランスを崩してしまうのです。
つまり山崎さんと松谷さんは腸腰筋が衰えていたので立ったまま靴下を履くことができなかったのです。
このように歩く・座るなどの動きや上半身のバランスを保つなど、大切な働きをする腸腰筋、この筋肉が体の不調と密接に関係しているといいます。
体の不調、クロスシンドローム
「クロスシンドローム」は本来正常な筋肉のバランスが崩れてしまった状態です。
私たちの体は筋肉同士が密接に繋がっていて腸腰筋など一つの筋肉が衰えると、反対側の筋肉にも衰えが生じます。
するとさらに隣り合う筋肉が連鎖的に影響を及ぼします。
やがては全身の筋肉が衰えてしまうんです。
その影響し合う筋肉を線で結ぶととクロスを描くため、「クロスシンドローム」と呼ばれています。
中でも身体の中心に位置する腸腰筋の影響は大きく、山崎さんは腸腰筋が衰えるで連鎖的に腰痛に、松谷さんにいたっては、連鎖的に肩の筋肉も衰えて腰痛・肩こりに繋がったと考えられます。
また、筋肉の影響が全身に及ぶことで頭痛や関節痛といった不調にも繋がってしまいます。
なぜ腸腰筋が衰える?
では、なぜ腸腰筋は衰えてしまうのか。
実は普段の行動に原因があります。
原因:足を組む
足を組むと腸腰筋が個人固まりやすく塀とか脚を組むとお腹と太ももの距離が近づきます。
すると、腸腰筋が圧迫され、血流が悪くなり、機能が低下して衰えに繋がってしまうんです。
原因:前傾姿勢
スマホなどを見るときは前傾姿勢になってしまうため、足を組むのと同様、お腹と太ももの距離が近づき、腸腰筋が衰えてしまいます。
特に仕事で長時間座っている人は時間と共に、前傾姿勢になりがちなので注意してください。
原因:すり足
すり足は本来の歩き方と比べ、腸腰筋そのものが使えていない歩き方であるため、腸腰筋が衰えやすくなります。
原因:浅く座る
椅子やソファに浅く座る。
この姿勢だと上半身を背もたれに預けることで腸腰筋を使われていない座り方になってしまい、腸腰筋が衰えやすくなります。
原因:猫背
猫背は背中が丸まった楽な姿勢だが、これは浅く座るのと同様、腸腰筋があまり使われていないため、衰えに繋がってしまいます。
要注意!メタボリックシンドロームの人は腸腰筋が衰えやすい
メタボリックシンドロームの人は衰えやすいとのことです。
お腹が出てる分、重さで重心が前になり、それを戻そうとして前傾姿勢になります。
そのため、股関節の前にある部分の距離が近くなって、腸腰筋が縮こまって衰えやすくなります。
衰えた腸腰筋の機能を今からでも取り戻せる!
衰えた腸腰筋の機能は今からでも取り戻すことができます。
腸腰筋が復活!簡単ストレッチ「腸腰筋のばし」
腸腰筋の機能を回復するストレッチ、「腸腰筋伸ばし」。
- 椅子に横に座った状態で片足を後ろに持っていきます。
このとき、後ろ脚はできるだけ膝を伸ばすのがポイントです。 - 次に、おへそを突き出すように体重を前に乗せます。
- そしてこの姿勢を10秒間キープ。
たったこれだけです。
このストレッチを片足10秒ずつ朝昼晩3セット行いましょう。
前傾姿勢とは逆に体を反らすので、腸腰筋をしっかりと伸ばすことができます。
これにより、腸腰筋本来の機能を取り戻し、肩こり腰痛といった不調の予防改善が期待できます。
「大きいお風呂があればお風呂の中でやってもいいよね」と筧さん。
腸腰筋の衰えを加速させてしまう怖い病気がある?!
腸腰筋の衰えを加速させてしまうやっかいな病気があります。
それは「変形性股関節症」です。
骨盤と大腿骨の間に軟骨があり、その軟骨がだんだんすり減ってくるとどうしても骨同士で擦れてしまう状態になります。
そうすると炎症が起こって痛みが生じます。
これが「変形性股関節症」という病気です。
「変形性股関節症」と腸腰筋とはどんな関係が?
軟骨がすり減ると骨盤と股関節のはまり具合が浅くなります。
腸腰筋がそれらをうまくはめようと働き続けます。
すると、腸腰筋が酷使されて疲れてしまい、衰えてしまいます。
四、五十代で自覚症状が現れやすいという「変形性股関節症」。
その患者数はなんとおよそ500万人!
決して他人事ではありません。
また日本人は遺伝的要因でこの病気になる人が多いといわれています。
「変形性股関節症」チェック
- チェック1:足の爪切りがしづらくなった
- チェック2:長時間歩いた後、股関節がだるくなったり、痛みが出る
- チェック3:座ったときに片方の膝が前に出ている
当てはまる数が多いほど、変形性股関節症の可能性が高くなります。
「変形性股関節症」の予防方法
すり減った軟骨を元に戻すことはできません。
ですが、軟骨できるだけすり減らないように、予防法はあります。
それは、座っているときにボールが床に置いて足で前後左右にコロコロと転がすだけです。
ボールを足で転がすことで股関節の中にある潤滑油の役割をする関節液が分泌されます。
変形性股関節症は歩き始め、立ち上がって動き始めたときに痛みが出ます。
前もって関節液を出すことが大切です。動き出すための備えのようなものですね。
皆さんも身近なものを使って股関節の痛みを防ぎましょう。
「変形性股関節症」が改善したケースあり
このボールを転がすことは変形性股関節症を予防するだけではなく、すでに発症した人が、これを行ったところ、痛みが改善したケースもあります。
長期間行い続ける必要があります。
軽い痛みがある場合、諦めずにやっていただくことが大事です。

フォローお願いします